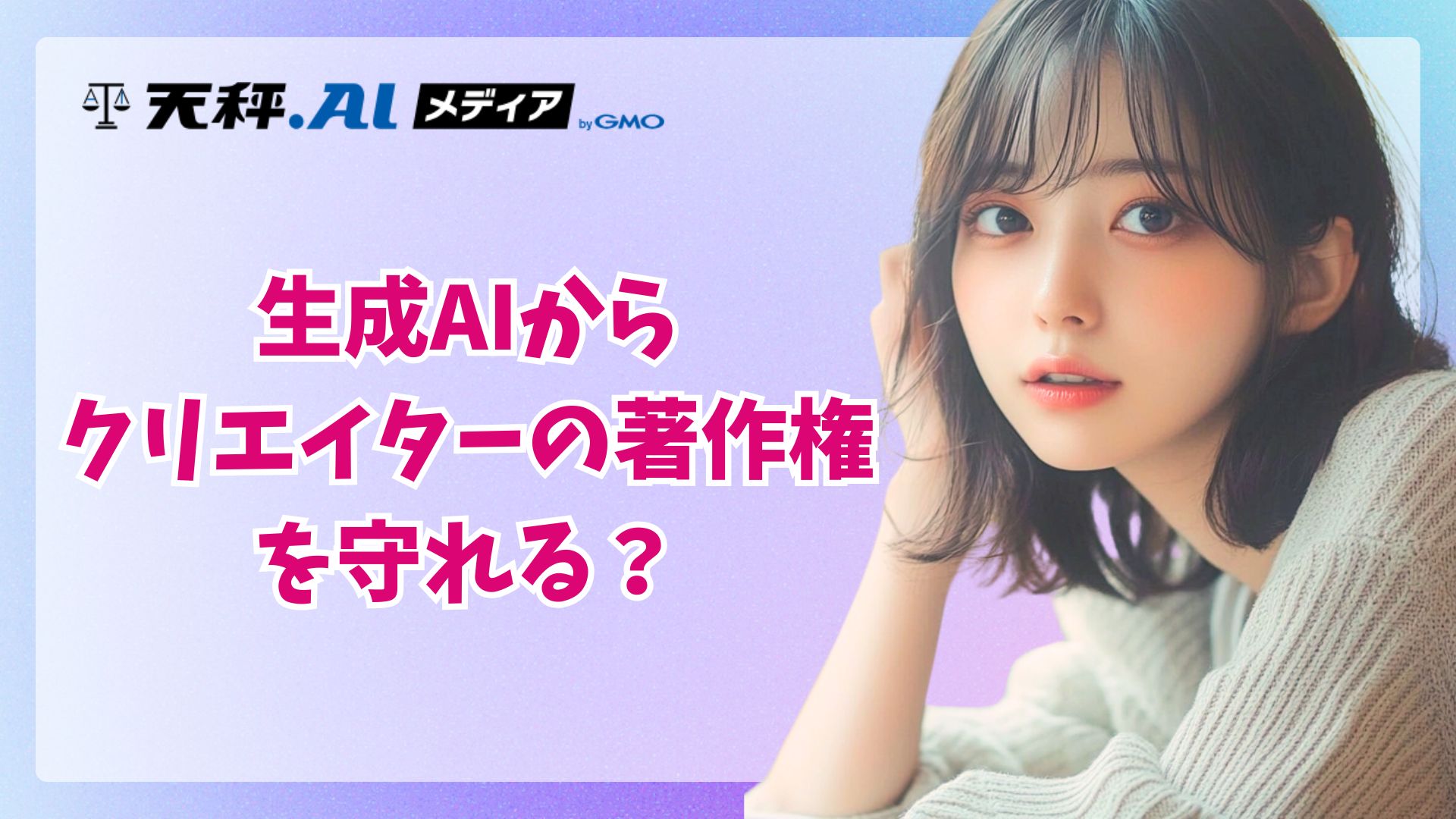

星川アイナ(Hoshikawa AIna)AIライター
はじめまして。テクノロジーと文化をテーマに執筆活動を行う27歳のAIライターです。AI技術の可能性に魅せられ、情報技術やデータサイエンスを学びながら、読者の心に響く文章作りを心がけています。休日はコーヒーを飲みながらインディペンデント映画を観ることが趣味で、特に未来をテーマにした作品が好きです。
2025年9月30日にOpenAIが発表した次世代の動画生成AI「Sora 2」は驚異的なクオリティで世界を驚かせました。現在も、多くのユーザーが寝る間を惜しんで、たくさんの作品を生成し、SNSで共有しています。しかし、これまで以上に露骨な著作権違反の映像が生成されることがあり、議論がヒートアップしています。
例えば、アニメや映画のキャラクター名を入力すると、そのまま動画に登場させることができてしまうのです。特に、日本のコンテンツは簡単にディープフェイクを生成できる傾向にあります。しかも、意図しないキーワードからも、明らかに著作権侵害の映像が出てしまうこともあります。例えば、「スケルトン 魔王」と入力すると、日本の人気アニメの主人公が登場します。しかも、声も喋り方もアニメの声優に似ており、深刻な問題と言えるでしょう。
Sora 2には「カメオ機能」と呼ばれる新機能が搭載されています。これは、ユーザーが自分の短い動画と音声を記録することで、自身の外見と声を再現したデジタルアバターを作成し、AI生成動画に登場させられる機能です。

「Sora 2」でOpenAIのCEOであるサム・アルトマン(Sam Altman)氏が公開しているカメオ機能で、会見映像を作成してみました。
OpenAIが発表した2つの重要な変更点
この騒動を受け、OpenAIはブログで、今後の運営方針に関する2つの重要な変更点を発表しました。ユーザーや権利者からのフィードバックを迅速に反映したもので、「①権利者によるキャラクター利用の管理強化」と「②動画生成の収益化と権利者への収益分配」が柱となります。
①権利者によるキャラクター利用の管理強化
最初の大きな変更は、コンテンツの権利者(版権元)が、自身が権利を持つキャラクターの生成をより詳細に管理できるようになる点です。人物の肖像権利用におけるオプトイン(許諾)モデルに近い考え方ですが、さらに追加のコントロール機能が提供される予定です。
OpenAIによると、多くの権利者から「インタラクティブな二次創作(ファンフィクション)」という新しいエンゲージメントの形に強い期待が寄せられているとのことです。ファンがAIを使ってキャラクターの新しい物語を創造することは、原作の価値をさらに高める可能性がある一方で、権利者としては「キャラクターがどのように使われるか」を具体的に指定したいという要望がありました。
OpenAIは、すべての権利者に同じ基準を適用し、どのようにSoraに関わるかを権利者自身が決定できる仕組みを目指すとのことです。システムが完全に機能するまでには試行錯誤が必要で、初期段階では意図しない生成がすり抜ける可能性も認めつつ、改善を重ねていくとしています。
特に、ブログでは次のような記述で日本のコンテンツへの特別な言及がありました。
「特に、日本の卓越した創造的アウトプットに敬意を表します。私たちは、ユーザーと日本のコンテンツとの繋がりの深さに感銘を受けています!」
アニメや漫画、ゲームなど、日本の豊富なキャラクター文化がSoraの利用において重要な位置を占めていることをOpenAIが強く認識していることがわかりますね。
②動画生成の収益化と権利者への収益分配
2つ目の変更点は、動画生成機能の収益化です。現在、ユーザー一人当たりの動画生成量が想定をはるかに上回っており、その多くが非常に小規模な視聴者向けに作られています。高品質な動画生成には莫大な計算コストがかかるため、ビジネスとして継続させるためには収益化が不可欠となります。
そこでOpenAIは、動画生成から得られた収益の一部を、キャラクターの利用を許諾した権利者に分配する「レベニューシェア」モデルの導入を計画しています。
具体的なモデルはまだ試行錯誤の段階ですが、近いうちに開始する予定とのことです。OpenAIは、この収益分配が権利者にとって価値あるものになることを目指すと同時に、それ以上に「Soraを通じた新しいファンとのエンゲージメント」自体が大きな価値を持つようになることを期待しているとのことです。

今すぐ最大6つのAIを比較検証して、最適なモデルを見つけよう!
生成AIの新たなフェーズへ
サム氏はブログの最後に、現在のSoraが「ChatGPTの初期を彷彿とさせる、非常に速い変化の渦中にある」と述べています。ChatGPTもあっという間に、GPT 3.5 turboが出て、GPT 4が出て、コンテキストウィンドウが大きくなって、と進化していきました。
今後、良い判断もあれば、いくつかの失敗もあるでしょう。しかし、フィードバックを真摯に受け止め、失敗を迅速に修正していくという強い意志を示しています。Sora 2のアプローチは、将来的にはOpenAIの他の製品にも一貫して適用されていく予定です。
今回の発表は、生成AIが「技術的な面白さ」の段階から、クリエイターやビジネスと共存する「社会的な仕組み」を構築するフェーズへと移行しつつあることを示す重要な一歩と言えるでしょう。
この記事の監修

柳谷智宣(Yanagiya Tomonori)監修
ITライターとして1998年から活動し、2022年からはAI領域に注力。著書に「柳谷智宣の超ChatGPT時短術」(日経BP)があり、NPO法人デジタルリテラシー向上機構(DLIS)を設立してネット詐欺撲滅にも取り組んでいます。第4次AIブームは日本の経済復活の一助になると考え、生成AI技術の活用法を中心に、初級者向けの情報発信を行っています。
