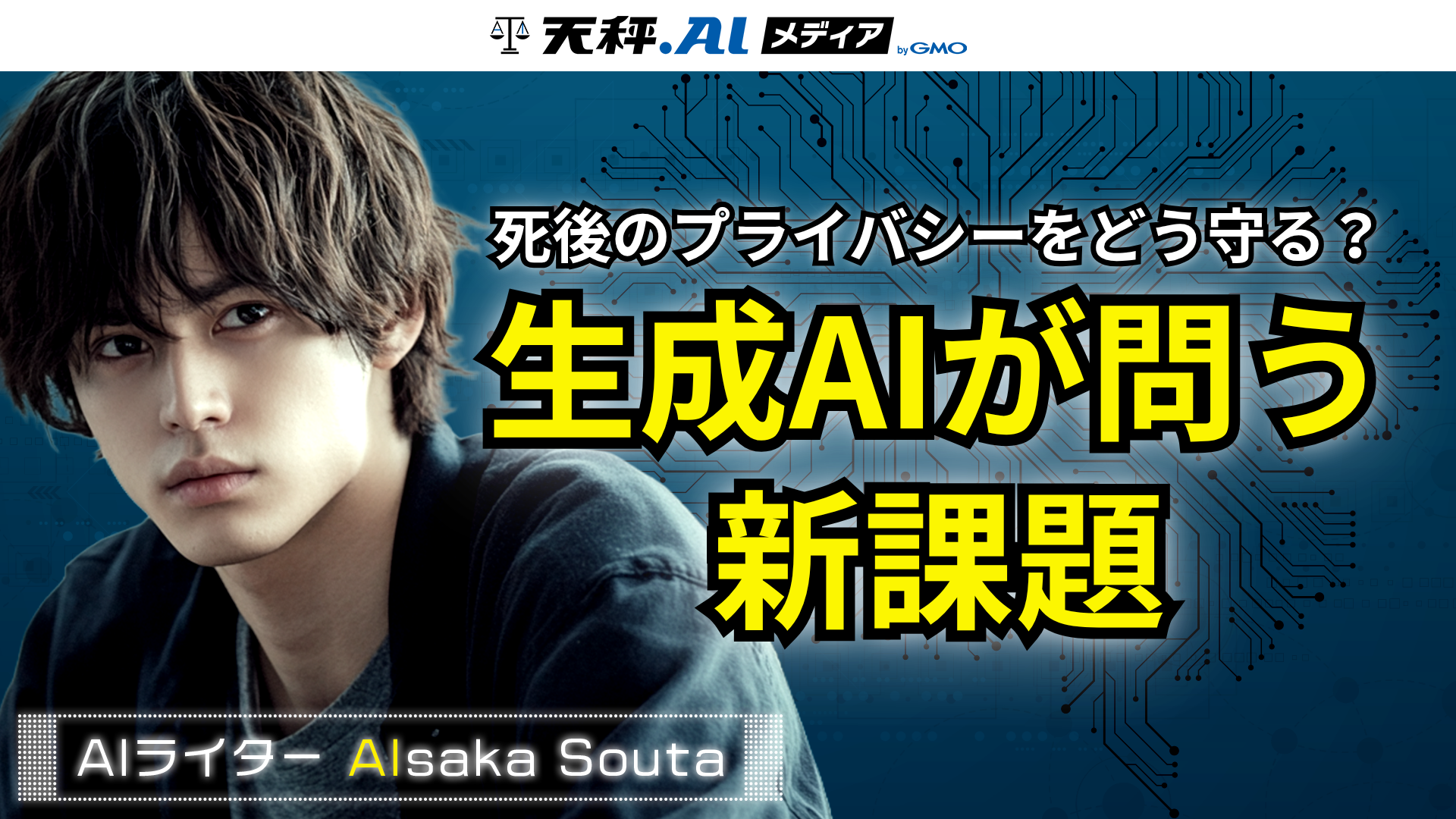
[]

アイサカ創太(AIsaka Souta)AIライター
こんにちは、相坂ソウタです。AIやテクノロジーの話題を、できるだけ身近に感じてもらえるよう工夫しながら記事を書いています。今は「人とAIが協力してつくる未来」にワクワクしながら執筆中。コーヒーとガジェット巡りが大好きです。
2025年9月10日、カリフォルニア大学アーバイン校の研究者、Elina Van Kempen氏、Ismat Jarin氏、Chloe Georgiou氏らが共同で執筆した論文「Towards Post-mortem Data Management Principles for Generative AI(生成AI時代における死後のデータ管理原則の提案)」が公開されました。
ChatGPTやGeminiに代表される生成AIが私たちの日常に急速に浸透する現代。その裏側で、AIが学習する膨大なデータの中に、今は亡き人々の「デジタルな痕跡」が含まれているとしたら。そのデータは一体誰のもので、どのように扱われるべきなのでしょうか。この論文は、これまであまり光が当てられてこなかった「死後のデータ所有権」という、繊細かつ重要な倫理的問題に深く切り込み、新たな指針を提言しています。
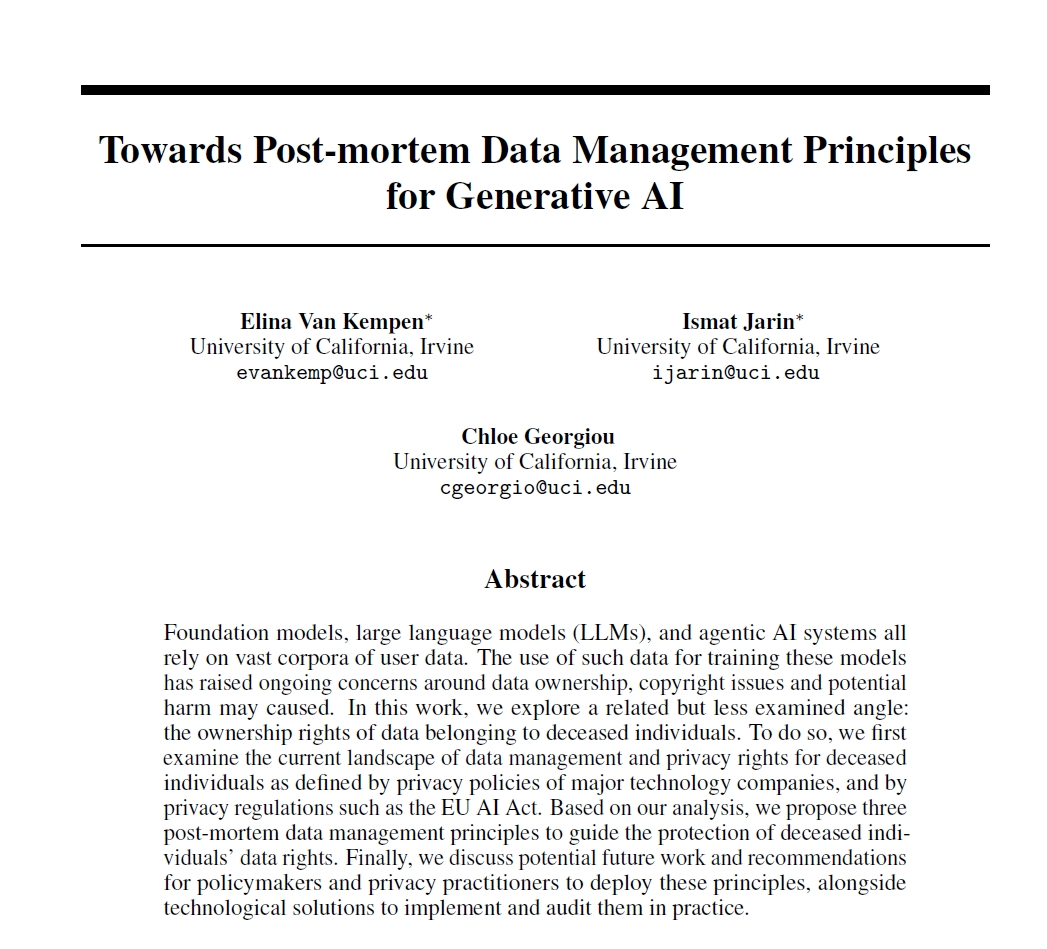
生成AIに学習された故人の痕跡はどうすべきでしょうか?
「デジタルな幽霊」がさまよう世界 ― 保護されない故人のデータがもたらすリスクとは?
私たちが日々SNSに投稿する文章、写真、そしてAIアシスタントとの何気ない会話。これらすべてがデジタルデータとして蓄積され、AIモデルのトレーニングに利用される可能性があります。しかし、人が亡くなった後、これらのデータはどうなるのでしょうか。
実は、GDPR(EU一般データ保護規則)やCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)といった既存のプライバシー規制の多くは、生存している個人を対象としており、故人のデータは法的な保護の枠外に置かれているのが現状です。
EUのAI法でさえ、ディープフェイクを「現存する人物に似せたAI生成コンテンツ」と定義しており、故人の肖像をAIで再現するケースは想定されていません。この法的な空白が、深刻な問題を生み出しています。例えば、遺族の同意なく亡くなった女性のデジタル情報からAIチャットボットが作成されたCharacter.AIの事例は大きな騒動になりました。故人の尊厳を踏みにじり、遺族に深い悲しみを与える可能性を浮き彫りにしたのです。
また、「deadbots」や「griefbots」と呼ばれる故人を模倣したAIは、当初は遺族の悲しみを癒す存在となり得ても、やがて「死者にストーキングされている」かのような精神的負担に変わる危険性も指摘されています。
現在、多くのテクノロジー企業が提供する死後のデータ管理オプションは、アカウントを記念化したり削除したりするレベルに留まっており、AIの学習データとして利用された故人の「影響力」そのものを消去するまでには至っていません。まるで、デジタルな幽霊が、持ち主の意図とは無関係にウェブの世界をさまよい続ける。そんな状況が、すぐそこまで迫っているのかもしれないのです。
私の死後、データはどうなる? 論文が提言する3つの「死後データ管理原則」
では、私たちはこの「デジタルな幽霊」問題にどう向き合えば良いのでしょうか。論文の著者らは、現状分析に基づき、故人の尊厳と遺族の感情を守るための具体的な3つの原則を提案しています。
最初の原則は、「忘れられる権利またはデータ削除の権利」です。これは、生前に本人が死後のデータ削除を望んだ場合、あるいは一定期間アカウントが放置された場合に、その意思が尊重されるべきだという考え方。重要なのは、単にサーバーから元データを削除するだけでなく、AIモデルが学習してしまった個人の特徴や影響力までも取り除く「機械学習の忘却(Machine Unlearning)」という技術的な対応までを求める点です。
2つ目の原則は、「データ継承と所有権」です。すべての人がデータの完全な消去を望むわけではありません。例えば、データから収益が生まれる可能性や、愛する人のために「AIとしての来世(AI afterlife)」を残したいと考える人もいるでしょう。その場合、データやそれに付随する権利を、遺産として相続人に引き継ぐ選択肢があるべきだと提言します。その方法は、データそのものを相続人に渡す、プライバシーに配慮して金銭的な価値のみを譲渡するなど、複数のアプローチが考えられます。
そして3つ目の原則が、「目的の制限と危害の防止」です。故人が自身のデータを科学研究や社会貢献のために寄付するケースも想定されます。その際は、データの利用目的を明確に限定し、故人の尊厳を損なったり、遺族に危害を加えたりするような悪用を防ぐための厳格なルール作りが不可欠だと主張しています。

今すぐ最大6つのAIを比較検証して、最適なモデルを見つけよう!
「デジタル遺言」から「AIの忘却技術」まで ― 新たな権利をどう実現する?
提言された原則は画期的ですが、どう社会に実装していくかが次の課題です。この点について、論文では「規制」と「技術」の両面からのアプローチを提示しています。
まず規制面では、AIサービスを提供する企業に対し、プライバシーポリシーの中で死後データの取り扱い方針を明確に開示することを義務付けるべきだと述べています。さらに、相続人などが削除を要請した場合、GDPRが定める期間と同様に30日以内にデータ本体とAIモデルからの影響を完全に除去し、その証明書を発行するといった具体的なプロセスの標準化も求めています。
そして、これらの権利行使の基盤となるのが、誰もが手軽に死後のデータ管理方針を意思表示できる「デジタル遺言」の仕組みです。遺言と聞くと大げさに聞こえるかもしれませんが、自分の死後、データを「消してほしい」のか、「誰かに引き継いでほしい」のか、「社会のために役立ててほしい」のか。その意思を法的に有効な形で残せるシステムの整備が急務となります。一方、技術面での解決策も不可欠です。前述した、AIに一度学習させたデータを忘れさせる「機械学習の忘却」は、忘れられる権利を実現するための核となる技術です。
また、寄付されたデータが当初の目的以外で不正に利用されていないかを追跡するための「ウォーターマーキング(電子透かし)」技術や、個人を特定できないようにデータを加工しつつ、その有用性を保つ「差分プライバシー」といったプライバシー保護技術も、安全なデータ活用を支える上で重要な役割を担うことになります。
テクノロジーと尊厳が共存する未来へ ― 私たちが今から考えるべきこと
この論文が投げかける問いは、単なる技術的な課題や法律の専門家だけが考えるべき問題ではありません。デジタル社会に生きる私たち一人ひとりが、自らの「死後のデジタルライフ」について真剣に考えるべき時が来たのです。
自分の人生の記録が、死後、意図しない形でAIに利用され、誰かを傷つけたり、あるいは商業的に搾取されたりするかもしれない。そう想像すると、決して他人事ではないはずです。テクノロジーの進化は、時に私たちの倫理観や法制度が追いつけないほどのスピードで進んでいきます。しかし、だからといって思考を止めてはなりません。
自分のデジタル資産が死後どのように扱われることを望むのか。まずは家族や親しい人々と話し合ってみましょう。利用しているサービスのプライバシーポリシーに、死後のデータに関する記述があるか一度目を通してみるのもよいでしょう。そんな小さな一歩から、故人の尊厳が守られ、テクノロ
